秋の読書週間期間中(2023/10/27-11/9)、ブックレビューに多数のご応募、ありがとうございました。
皆さんのおススメ図書と紹介文を案内します。
神谷美恵子著「生きがいについて」(みすず書房 1966年)
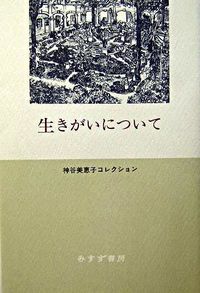 「毎日の生活を生きるかいあるように感じさせているものは何であろうか。」ハンセン病患者の精神医療に従事した著者の生きがいに関する書。医療者になったばかりの悩み多い時にこの本に出合い、眉が開かれる思いがした。また仕事と家庭の両立に悩んだ際の支えにもなった。以来、著者は私の人生の師であり、目標である。(M.N.)本学所蔵081.6||K||1
「毎日の生活を生きるかいあるように感じさせているものは何であろうか。」ハンセン病患者の精神医療に従事した著者の生きがいに関する書。医療者になったばかりの悩み多い時にこの本に出合い、眉が開かれる思いがした。また仕事と家庭の両立に悩んだ際の支えにもなった。以来、著者は私の人生の師であり、目標である。(M.N.)本学所蔵081.6||K||1本田健著「40代にしておきたい17のこと」(大和書房 2011年)
普段本を読まない私だが、待ち合わせの時間に早く着き、たまたま手にした本。
何度読み返しても、首を縦に振る場面が多くて、手放せない一冊となった!(M.S.) 京都市洛西図書館所蔵
何度読み返しても、首を縦に振る場面が多くて、手放せない一冊となった!(M.S.) 京都市洛西図書館所蔵
内村鑑三「人生、何を成したかよりどう生きるか」(文響社 2021年)
 31年前、当時まだ総理になられる前の細川護熙氏の講演を大学祭で聞いた。そのとき紹介された「誰にでも遺せる最大遺物は、勇気ある高尚なる生涯である」という言葉がいまだに耳に残っている。本書はその原典である内村鑑三の明治27年の講演の口語訳と解説。130年近く前の話が、先の見えない時代を生き抜く参考になる。(中央研究室RI部門 勝山真人)京都市伏見中央図書館所蔵
31年前、当時まだ総理になられる前の細川護熙氏の講演を大学祭で聞いた。そのとき紹介された「誰にでも遺せる最大遺物は、勇気ある高尚なる生涯である」という言葉がいまだに耳に残っている。本書はその原典である内村鑑三の明治27年の講演の口語訳と解説。130年近く前の話が、先の見えない時代を生き抜く参考になる。(中央研究室RI部門 勝山真人)京都市伏見中央図書館所蔵松尾健治「組織衰退のメカニズム」(白桃書房 2022年)

あなたが目指す「あるべき姿」はなんですか?
もし、その「あるべき姿」があなたの人生を衰退させてしまうとしたら、すぐに方向性を変えることができますか?
その戦略は本当に正しいですか?
本書では、成功の罠が解き明かされます。
著者の熱量が、あなたのこれからの人生に必要な知恵を授けます。
この本の熱さと厚さに、私は憧れています。(M.M.)本学所蔵335.1||M
もし、その「あるべき姿」があなたの人生を衰退させてしまうとしたら、すぐに方向性を変えることができますか?
その戦略は本当に正しいですか?
本書では、成功の罠が解き明かされます。
著者の熱量が、あなたのこれからの人生に必要な知恵を授けます。
この本の熱さと厚さに、私は憧れています。(M.M.)本学所蔵335.1||M
牧野富太郎「原色牧野植物大圖鑑」(北隆館 1982年)
今年一躍脚光を浴びた人物といえば、「日本の植物学の父」牧野富太郎博士。その牧野博士の『原色牧野植物大圖鑑』が、医大図書館に所属があることを知ったのは、この夏、図書館カウンター前で催された“雑草という草はない“の企画展示でした。彩色図による彩り美しく繊細な植物画にページを捲るたびに心癒されます。道端でフッと目にした植物の名前をあなたも調べてみませんか?(N.A.)本学所蔵470.38||M||1
大竹文雄、平井啓「医療現場の行動経済学: すれ違う医者と患者」(東洋経済新報社 2018年)
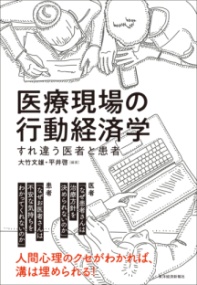 医者と患者とで、医療行為の受け止め方に違いがあるのはなぜか。人間の意思決定にひそむさまざまバイアスについて、たくさんの具体例とともに行動経済学の視点で解説されている。私がこれまで患者にあわせて漠然と説明の仕方を変えていたことの意味づけをズバッと専門用語で説明されていて、まさに腑に落ちた一冊。(M.U.)本学所蔵 下鴨館490.14||O
医者と患者とで、医療行為の受け止め方に違いがあるのはなぜか。人間の意思決定にひそむさまざまバイアスについて、たくさんの具体例とともに行動経済学の視点で解説されている。私がこれまで患者にあわせて漠然と説明の仕方を変えていたことの意味づけをズバッと専門用語で説明されていて、まさに腑に落ちた一冊。(M.U.)本学所蔵 下鴨館490.14||Oダ・ヴィンチ編集部「病院で読むということ」(メディアファクトリー 1998年)
入院は読書のチャンス。私も持参する本選びに苦心した。藁をもつかみたい心境では「がんが自然に治る」など、少々怪し気な本も心の支えになる。
この本は、実際にどんな病気の人がどんな本を読んだか、発病や退院後の経過まで記された48編+書下し4編。内科は長編、整形外科はスポーツ関連、婦人科は家族の話など、診療科目によって何となく特色が見られるのも興味深い。(C.H.)本学所蔵490.4||D
この本は、実際にどんな病気の人がどんな本を読んだか、発病や退院後の経過まで記された48編+書下し4編。内科は長編、整形外科はスポーツ関連、婦人科は家族の話など、診療科目によって何となく特色が見られるのも興味深い。(C.H.)本学所蔵490.4||D
海堂尊「トリセツ・カラダ カラダ地図を書こう」(宝島社 2009)
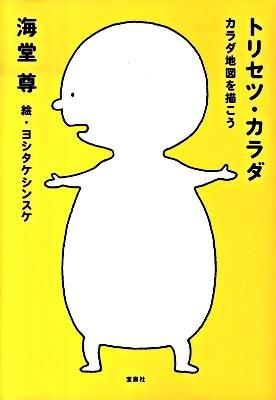 かの有名な海堂尊先生の本と言うことで手に取りました。カラダの構造や組み立て、おおよその理解が得られる最小の説明でありながら最大の理解が得られる良書です。
かの有名な海堂尊先生の本と言うことで手に取りました。カラダの構造や組み立て、おおよその理解が得られる最小の説明でありながら最大の理解が得られる良書です。2時間あれば読めますが、そのあとでは身体に対する理解が変わります。中学生くらいからこの本に触れて身体の概観を掴むのは素敵な体験だと思いました。もちろん大人でも。(薬剤部 小西洋子)本学所蔵491.3||K
藤田晢也「脳の履歴書:幹細胞と私」(岩波書店 2002)
神経発生学におけるマトリックス細胞説という業績を遺し、本学学長も務めた著者による、研究生活を中心とした回想記。冒頭の病理学教室入局のエピソードに示されたように、輝かしいサクセスストーリーというよりも、その都度、訪れる試練に挑み、新しい知見や技術を得ながら進んでいく物語として面白く読める。(R.M.)本学所蔵491.371||F
手良向聡、山本景一、河野健一編「ヘルスデータサイエンス入門」(朝倉書店 2023)
ヘルスデータサイエンスという新しい学問分野の全体像に関する入門書である.近年,医療・健康の領域においても大量のデータが容易に手に入るようになってきた.しかし,大量のデータがあれば,何か役に立つ情報が必ず得られるとは限らない.ということから、このような学問分野が必要になる.(生物統計学 手良向聡)本学所蔵498.019||T
土井善晴「一汁一菜でよいという提案」(グラフィック社 2016)
忙しい日々を送る現代にあっておざなりにされがちな家庭料理。しかしそこにこそ「食」の本質があると筆者は言います。日本の伝統的な食の流れを汲みつつも、楽に整えられる「一汁一菜」のスタイルを取り入れることで、自然の恵みや人の繋がりを感じながら穏やかに食事を楽しめるようになりました。日々の茶飯事が輝いて見えるようになる一冊です。(M.K.)京都市右京中央図書館所蔵
有吉佐和子「華岡青洲の妻」(新潮社 1967)
華岡青洲は世界で初めて全身麻酔下での外科手術に成功した医師として有名であるが、その裏には母と妻の尊い犠牲、嫁と姑の愛憎や嫉妬の入り混じる戦いがあった。そんな読み物としての面白さも含みつつ、医療従事者として働く身としては、新薬の開発や成功はそんな犠牲の上に立つものであると、教訓めいたことをしみじみと感じずにはいられない。(S.K.)本学所蔵集密書架上層 913.6||A
水野敬也「夢をかなえるゾウ」(飛鳥新社 2011)
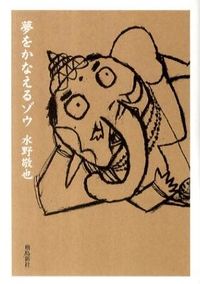 いつ買ったのかも覚えていないが、1度読んで気に入ってから何となく本棚に眠らせていた一冊である。
いつ買ったのかも覚えていないが、1度読んで気に入ってから何となく本棚に眠らせていた一冊である。
「自己啓発」というと大層なことのように感じてしまう。しかしこの本の中ではあるはちゃめちゃな''神様''が、日常の些細な所に自分を変えるヒントがあるということを教えてくれる。
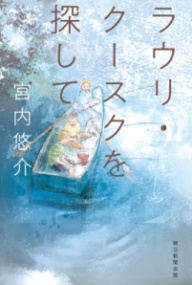 ソ連解体の激動の中で、エストニアの行方不明の天才プログラマー、ラウリ・クースクを探すロシア人記者の手記の形をとる小説。翻弄される人間模様が主題だが、自身もプログラマーである著者の、基本的なプログラムセンスを読者に導く手腕に感服する。歴史との整合性も高く、登場人物たちがまるで実在であるかのような錯覚に陥る。(M.S.)京都府立図書館所蔵
ソ連解体の激動の中で、エストニアの行方不明の天才プログラマー、ラウリ・クースクを探すロシア人記者の手記の形をとる小説。翻弄される人間模様が主題だが、自身もプログラマーである著者の、基本的なプログラムセンスを読者に導く手腕に感服する。歴史との整合性も高く、登場人物たちがまるで実在であるかのような錯覚に陥る。(M.S.)京都府立図書館所蔵
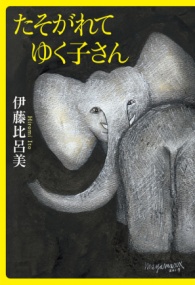 三度の結婚、三人の子育て、両親の看取りを経験した米在住(当時)の詩人が年の離れた英国人の夫を看取る日々を綴ったエッセイ。誰もがいつか迎える人生の黄昏時を「怖くないよ」と優しくおおらかに教えてくれる一冊。(Y.S.)京都府立図書館所蔵
三度の結婚、三人の子育て、両親の看取りを経験した米在住(当時)の詩人が年の離れた英国人の夫を看取る日々を綴ったエッセイ。誰もがいつか迎える人生の黄昏時を「怖くないよ」と優しくおおらかに教えてくれる一冊。(Y.S.)京都府立図書館所蔵
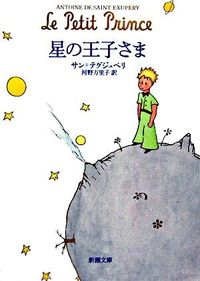 なんとなく手放せずに、小学校の読書課題で買わされたものを持ち続けていたが、さすがに古くなったので新調した。手に取るのは年に1度程度なのだが、読む度に「こんなことを言っていたのか、」と、妙に腑に落ちる部分が見つかる不思議な本だと思う。日常に埋もれてしまう自分の中のピュアな部分を、もう一度蘇らせてくれる旧友のような存在。 (R.I.)京都市中央図書館所蔵
なんとなく手放せずに、小学校の読書課題で買わされたものを持ち続けていたが、さすがに古くなったので新調した。手に取るのは年に1度程度なのだが、読む度に「こんなことを言っていたのか、」と、妙に腑に落ちる部分が見つかる不思議な本だと思う。日常に埋もれてしまう自分の中のピュアな部分を、もう一度蘇らせてくれる旧友のような存在。 (R.I.)京都市中央図書館所蔵
この本の主人公と共に、自分自身を振り返ってみてはいかがだろうか。(M.K.)京都市中央図書館所蔵
宮内悠介「ラウリ・クースクを探して」(朝日新聞出版 2023)
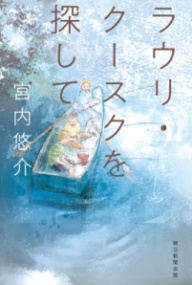 ソ連解体の激動の中で、エストニアの行方不明の天才プログラマー、ラウリ・クースクを探すロシア人記者の手記の形をとる小説。翻弄される人間模様が主題だが、自身もプログラマーである著者の、基本的なプログラムセンスを読者に導く手腕に感服する。歴史との整合性も高く、登場人物たちがまるで実在であるかのような錯覚に陥る。(M.S.)京都府立図書館所蔵
ソ連解体の激動の中で、エストニアの行方不明の天才プログラマー、ラウリ・クースクを探すロシア人記者の手記の形をとる小説。翻弄される人間模様が主題だが、自身もプログラマーである著者の、基本的なプログラムセンスを読者に導く手腕に感服する。歴史との整合性も高く、登場人物たちがまるで実在であるかのような錯覚に陥る。(M.S.)京都府立図書館所蔵伊藤比呂美「たそがれてゆく子さん」(中央公論社 2021)
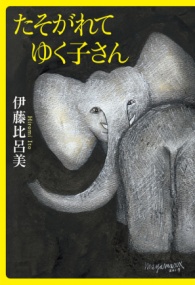 三度の結婚、三人の子育て、両親の看取りを経験した米在住(当時)の詩人が年の離れた英国人の夫を看取る日々を綴ったエッセイ。誰もがいつか迎える人生の黄昏時を「怖くないよ」と優しくおおらかに教えてくれる一冊。(Y.S.)京都府立図書館所蔵
三度の結婚、三人の子育て、両親の看取りを経験した米在住(当時)の詩人が年の離れた英国人の夫を看取る日々を綴ったエッセイ。誰もがいつか迎える人生の黄昏時を「怖くないよ」と優しくおおらかに教えてくれる一冊。(Y.S.)京都府立図書館所蔵溝渕カミ「笑うオカン戦士:溝渕カミ闘病2000日」(ぴあ関西支社 2011)
無事大学への合格が決まり、実家から京都へ向かう前日、母が私にこの本を手渡してきました。この本は、著者のカミさんが難病「ゼザリー症候群」だと申告されてからの日々が日記のように書かれたお話です。急に難病と宣告されたカミさんやその家族の姿に感極まって涙を流してしまう場面もありました。しかし、最後まで難病に負けることなく生き抜くカミさんから勇気をたくさんもらいました。(K.K.)京都府立図書館所蔵
サン=テグジュペリ 河野万里子訳 「星の王子さま」(新潮社 2006)
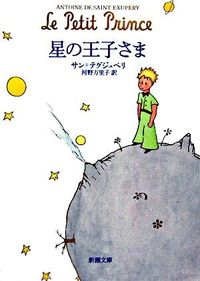 なんとなく手放せずに、小学校の読書課題で買わされたものを持ち続けていたが、さすがに古くなったので新調した。手に取るのは年に1度程度なのだが、読む度に「こんなことを言っていたのか、」と、妙に腑に落ちる部分が見つかる不思議な本だと思う。日常に埋もれてしまう自分の中のピュアな部分を、もう一度蘇らせてくれる旧友のような存在。 (R.I.)京都市中央図書館所蔵
なんとなく手放せずに、小学校の読書課題で買わされたものを持ち続けていたが、さすがに古くなったので新調した。手に取るのは年に1度程度なのだが、読む度に「こんなことを言っていたのか、」と、妙に腑に落ちる部分が見つかる不思議な本だと思う。日常に埋もれてしまう自分の中のピュアな部分を、もう一度蘇らせてくれる旧友のような存在。 (R.I.)京都市中央図書館所蔵












